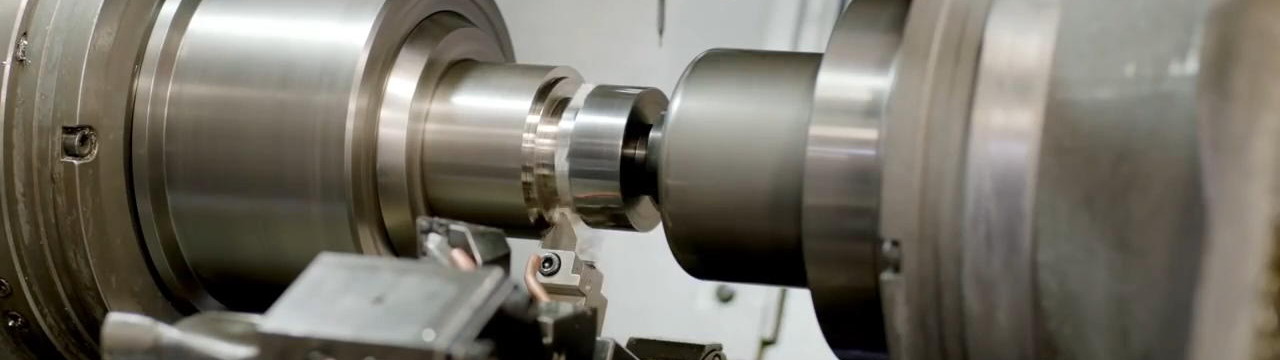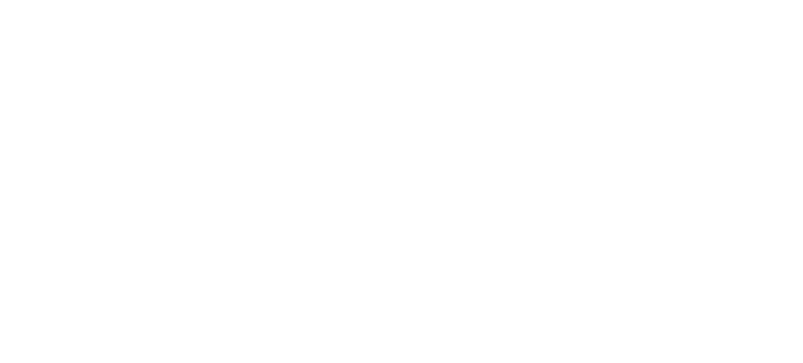ドバイ皮切りに出現!回転するビル
時代は四次元へ キーワードは「時間」
今年6月、イタリアの建築家であるデイビット・フィッシャー博士が、世界初の動く回転式超高層ビル「ダイナミック・タワー」をドバイとモスクワに建設すると発表した。「動きある有機的な生によって形作られ、時間によって設計された」と博士が語るこの建物は、日の出から日没まで各階が独立して360度回転し、まるで生き物のように全体の形を変化させる。各階で異なる回転時間・...
- 2009年01月09日

サーペンタインギャラリーパヴィリオン2008
建築界のピカソ、英国初上陸!?
ロンドン西部、ハイドパーク内のサーペンタインギャラリーに隣接するように、毎年夏季限定でパヴィリオンが建設され、カフェ、舞台などの要素を含む、フリースペースとして開放される。サーペンタインギャラリー自体の規模はそれ程大きくないが、世界のモダン&コンテンポラリーアートをテーマに数多くコレクションを所蔵しており、2002年に村上隆がエキシビジョンを行ったのは記憶に...
- 2009年01月09日

コルビュジエの建築22件、世界遺産申請へ
自己表現と自己実現の天才ル・コルビュジエ
ご存知のとおり、ル・コルビュジエは近代建築の代表的な建築家のひとりである。鉄筋コンクリートを用いた住宅建設方法「ドミノシステム」、「住宅は住むための機械である」という自身の建築思想を的確に表現した言葉。さらには近代建築の5原則、「ピロティ」「屋上庭園」「自由な平面」「水平に連続する窓」「自由な立面(ファサード)」を発表し、1928年「サヴォワ邸」に...
- 2009年01月09日

渋谷の中心に出現する地宙船
コンセプトは建築家、安藤忠雄氏
東京の情報発信地である渋谷に新たな名所が登場する。6月14日の東京メトロ副都心線の開通に伴い開業した
東急東横線・東京メトロ副都心線渋谷駅がそれである。東京メトロ副都心線と東急東横線の相互運転開始は
2012年度を予定しており、東急電鉄では同駅東口の旧東急文化会館跡地に建設予定となっている複合高層ビル
の開発を進めている。新渋谷駅の構想・デザインは世界的建築...
- 2009年01月09日

LUX BOOK REVIEW『きもちのいい家』
住む人の「きもちいい」ができるまで
手塚夫妻はTBS系『情熱大陸』で放映された話題の建
築家。話題といっても、シンボリックな何かを手がけ
たわけではない。彼らが作るのは家族がごく普通に
暮らす家だ。それもゴロゴロしながら本を読んだり、
ボーッとしていても「気持ちがいい」と思える家。そ
んな「ありそうでなかった当たり前のこと」を大切に
しながら、二人がどんな家を作ってきたのかを紹介
したのが...
- 2009年01月09日

LUX BOOK REVIEW『ル・コルビュジェ 全作品ガイドブック』
建築作品に込められた夢と思想に肉迫
ル・コルビュジェは、近代建築の三大巨匠の一人。ス
イス生まれでパリで活躍し、世界各国に多くの作品
を残してきた。日本でも、上野にある国立西洋美術館
は、彼が基本建築を手がけたものだ。この本では、建
築家ル・コルビュジェの全作品を紹介している。その
多くは、個人の邸宅や集合住宅、合同庁舎や墓碑など
生活と密着したものだ。彼は一軒の家にも、彼の理想
と思想を...
- 2009年01月09日

LUX BOOK REVIEW『民家のしくみ』
古き良き家の知恵と工夫を学ぶ
「200年住宅」という言葉を耳にしたことがあるだろうか。サステナブル社会に向けて、長持ちする住宅を作っ
ていこうという動きだ。そこで注目されているのが古き良き時代の家。無駄なエネルギーを使わず、知恵と
工夫で快適な暮らしを実現する「民家」だ。 この本は日本全国に点在する民家を紹介している。どのように
雪や風を凌いでいるのか。どんな工夫で光を取り入れているのか。...
- 2009年01月09日

LUX BOOK REVIEW 『ガウディが知りたい』
ガウディの魅力と謎の集大成
どこから読んでも丸ごとガウディ。この本は世界遺産
に3つも作品をエントリーさせている天才建築家・ガウ
ディの魅力を満載した贅沢なムック本。ガウディはど
んな人間だったのか、何を目指していたのか、そしてガ
ウディの作品のどこに人々は魅了されるのかを
様々な視点から紐解いている。寄稿しているのは、日
本や世界で活躍する建築家やアーティスト。ひとつひ
とつに興味深いエ...
- 2009年01月09日

ジェフリー・バワ 「熱帯建築」の世界
スリランカが生んだ天才建築家
ジェフリー・バワ。日本では知る人ぞ知る存在だが、トロピカルアーキテクチャーの第一人者として、世界に名を
馳せる人物である。今や、最高級リゾートの代名詞でもある『アマン・リゾート』の創始者、アイドリアン・ゼッカ
もが心酔し、バワから多大な影響を受けていたと公言している。祖国、スリランカを愛し、時代を超えて愛される
名建築の数々の残したバワは、スリランカの国民的英...
- 2009年01月09日

新旧入り交じる八重山建築のいま
古き良き時代の建築が残る竹富島
沖縄の建築様式と聞いて多くの人は赤瓦を思い浮か
べる。しかし実際には沖縄本島を中心にその数が減
ってきているのが現状である。そんななか、八重山諸
島にある竹富島では今日でも沖縄の赤瓦家屋を島全
体で保存に努めている。竹富島は約350人が暮らす小
さな島で赤瓦、星砂、水牛といった、古き良き沖縄の
姿を連想させる要素を今なお多く持つ。特に建築物
に関しては島の公...
- 2009年01月09日

構造美×装飾美 〜イスラーム建築の流儀〜
モスクは、雄大荘厳であれ。
比類なき存在感とシンメトリーの美しさ、そして静粛
性。イスラーム建築の独自性は、これらの特徴に要約
できる。特に、イスラームの国々の各所に建てられて
いる礼拝所のモスクは、歴史的に地域の中心として機
能してきたため、古来からの特徴が表れているのだ。
圧倒的な存在感を持つ理由はいくつか考えられるが、
特筆すべきはシンプルなデザインと設計によって成
立...
- 2009年01月09日

独創的自然主義と生命 〜奇才ガウディの晩年〜
有機的な建築という史上初の試み
ガウディの建築物と出会うと、時が止まる。驚嘆からだ
ろうか、納得からだろうか、それともあまりに凄すぎて
唖然としてしまうからだろうか。おそらく、そのどれも
が正解で、答えはまだまだ他にもあるのだろう。冷静
に書くならば、ガウディのコンセプトの「自然主義」と
「独創性」から訪れたインスピレーションなのだが、と
てもひとことで書き表せるものではない。...
- 2009年01月09日

ジャン・ヌーヴェル 世界を眩惑する建築家
技術と素材を駆使し建築に現代性を反映
才能とビジョンある建築家を表彰する「プリツカー賞」。建築界のノーベル賞と評され、過去の受賞者にはフ
ランク・ゲーリー、リチャード・マイヤー、ノーマン・フォスターらが名を連ねる。この栄誉ある賞の2008年度
の受賞者となったのが、東京・汐留の電通本社ビルも手がけたフランス人建築家ジャン・ヌーヴェルである。
主催する米ハイアット財団は、授賞理由を「新...
- 2009年01月09日

変貌する中国 変貌する建築
都市部は世界の建築家の試験場
宇宙船のような塔や、卵のような施設、アルファベッ
トの「A」のような形状のビルなど、中国の都市部では奇
抜な形状の建物がどんどん生まれている。その勢いは
一般的なオフィスビルやマンションなども同様で、と
あるデータによると、なんと全世界で消費されるコン
クリートの4分の1が中国で消費され、3分の2のクレー
ンが稼働しているという。これらの現代建築やビルな
どは...
- 2009年01月09日

日本の味を アイスで楽しむ
「和」の素材を活かしたアイス
海外から多くのアイスクリーム、ジェラートのブランドが日本に進出し、マダガスカル産バニラビーンズやフランス、ベルギー産カカオを使った素材の産地までこだわる本格派アイスが登場してきている。そんな中、日本ならではの素材を使った「和」アイスとなるものが存在し、日本人として今まで食べ慣れてきたしょうゆや味噌などの調味料や旬の野菜を原料にしている。本特集では、一年を通して...
- 2009年01月09日

伝統相伝の技芸が調和を成した高雅なる和の極み
クレドール 漆芸コレクション
わが国の世界遺産候補として注目を集めた岩手県平
泉の国宝・中尊寺金色堂は平安時代後期に建立され
た。下地に漆を塗って布を着せた上に総金箔を施し、
柱に蒔絵と螺鈿の装飾、そして圧巻は漆芸で描
かれた仏堂内の壁画。これは当地で良質の漆が採れる
ことや、奈良時代に始まった日本独自の蒔絵の技と、同
時代に中国から伝来した螺鈿細工の技が平安時代に
盛んに併...
- 2009年01月09日

巨匠エンツォ・マーリが出会った日本
日本のものづくりの本質に迫るアウラコレクション
イタリアデザイン界の巨匠エンツォ・マーリ。伝統工芸から工業製品まで、あらゆるものの生産・流通に携わる人々とともに、創造活動のあり方を模索する彼が、日本のものづくりに向き合っている。
1950年初頭から視覚心理学、知覚構造の設計、デザイン方法論などを研究し、多彩な活動を展開してきたエンツォ・マーリは半世紀にわたってデザインの本質を探り、産業...
- 2009年01月09日

伝統とモダニズムの先へ wachaに集う人々
高橋氏は現在、東京・代々木の和カフェ「wacha」で、盆栽を楽しむ会を開いている。参加者はみな多忙を極める人たちなだけに、全員が同じ日に集まれるわけではないが、現在2か月に1度のペースで集まっているという。
Text Yuko Suzuki
Photo Tony
今をときめく多彩なメンバー
会のメンバーは会社オーナー、医師、デザイナー、ファションプロデューサー、ジャーナリスト……。今...
- 2009年01月09日

伝統とモダニズムの先へ 伝統美の饗宴
Text Yuko Suzuki
ジュエリーを引き立てた和美
「ショパール ウィズ チェリーブロッサム」が開かれたのは、東京に桜の便りが届く頃。エントランスに設えられ
た樹齢250年の堂々たる五葉松に迎えられ、会場に進むと、そこには金泥の屏風に蒔絵の長持や棚、艶やかな漆
の器、鼓、ひと足先に花をつけた寒桜やしだれ桜、真柏などの盆栽が。さながら平安の世の、春の宴のような中
で、ショパールの...
- 2009年01月09日

伝統とモダニズムの先へ 盆栽
Text Yuko Suzuki Photo Tony
盆の中で巡る四季
盆栽は文字通り、盆(鉢)の中で草木を栽培するもの。草木に命あるかぎり盆の中には四季が流れ、春には花が咲
き、夏は葉が青々と、秋には黄や赤へと色を変え、やがて枯れ落ちて冬を迎える。「四季折々に姿を変えていく草
木を見ていると、なぜか心が安らぎます。それは『四季を愛で、楽しむ』日本人のDNAでしょう。日本人ならではの
...
- 2009年01月09日

伝統とモダニズムの先へ 和への回帰
西洋ものへの憧れ
寺嶋氏はもともと西洋骨董、とくにアール・ヌーヴォーの品々が好きで集めていた。「理由は単純。日本のものと
は違ってデザインがモダンで、フォルムは凝っていてカラフルで、とにかくカッコイイと思ったんです。今にし
て思えば、それは私自身に日本の文化に対する知識や理解が足りず、『カッコイイ=西洋』と思い込んでいただ
けにすぎないのですが」。そして30代半ば、ロンドンを訪れた時のこと...
- 2009年01月09日

伝統とモダニズムの先へ 原点
日本の美の原点は“かざり”だった
かつて寺嶋氏が抱いていた日本文化・日本の美に対するイメージは、「わび」「さび」に代表されるように、デザイ
ンも色も「シンプルで控えめ」。あるいは、いわゆる民芸風の、どちらかといえば泥くささのあるものだった。「で
も、たとえば着物の色や柄。資料を見ると、時代を遡るほど斬新で華やかです。ところが何百年と時代を経るう
ち、“シンプル=モダン=カッコイイ”という傾...
- 2009年01月09日

伝統とモダニズムの先へ 1 日本の美
Text Yuko Suzuki Photo Tony
近年、わが国では見過ごされがちであった伝統文化、たとえば盆栽や漆器、禅などが「bonsai」「japan」「zen」と呼
ばれ,海外で高く評価されている。聞けば、そこにある、伝統とモダン、シンプルと華美、陰翳と絢爛といった強
いコントラストが面白いのだという。思えば「わび」「さび」は中世以降、茶の湯の発展によって生まれた美意識。
それ...
- 2009年01月09日

盆栽(2)——もっと親しみやすい遊びへ
盆栽の新しい形、「彩花盆栽」
自ら手がけるだけでなく、眺めているだけでも人は
盆栽から多くのことを学び、そして心癒やされる。た
だ、そこに樹齢や生命力の強さを求められるだけに価
値が出るまでに最低5年、枝が1本枯れると、それを補
う枝をつくるために10年、20年と途方もない時間がか
かる。だからこそ浪漫があり、人の心を惹きつけるのだ
が、やはり現代の生活のペースにはなじみにくい。そ
れが、...
- 2009年01月09日

盆栽(1)——それは想像力と戯れる遊び
人と人の心をつないできた盆栽
漆の「japan」と同じく、世界共通語となっている「盆栽=bonsai」。その起源は中国・唐王朝にあると言われなが
ら、日本の伝統文化として世界に認められているのは、草木を単に飾りものとしてではなく、日本人独特の感性
でそこに自然観を見出すという技法をもって表現したからであろう。
古めかしく厳かで、近寄りがたい雰囲気も漂う盆栽。それゆえ、一部の愛好者を除いて...
- 2009年01月09日

漆——自然が与え給うた命の器
漆を日本の食卓に取り戻したい
漆器を日本の生活に取り戻したい。それは、輪島だけでな
く、漆器を扱ってきた人たちすべての願いである。「それはも
ちろんビジネス上の話だけでなく、廃れつつある日本文化を
復興したいんです」と言うのは、東京・山田平安堂代表取締役
の山田健太氏。山田平安堂は創業90年を迎える漆器の老舗で
あり、宮内庁御用達ブランドとして、国内外に漆器のすばらし
さを伝え続けている。...
- 2009年01月09日

漆—— 潤し、麗わし、ニッポンの器
世界中の人々に愛されてきた「japan」
19世紀後半〜20世紀初頭、ヨーロッパ全土にジャポニ
スム旋風が吹き荒れた。きっかけはオランダを通じて
日本の工芸品が紹介された第3回パリ万国博覧会。そ
して1867年、開国後の幕府は第4回パリ万博に正式に
参加する。そこで薩摩藩、佐賀藩、民間から漆器や陶磁
器、絵画などが出品されたことによって、日本ブームに
火がついたのだ。ところが、それより3世...
- 2009年01月09日

杉本貴志展 鉄の茶室、水の茶室
既成概念のむこうに本質がある
92〜94年、東京と京都である展覧会が開かれた。亭主
は裏千家15代家元千宗室の次男・伊住政和、企画立案
はグラフィックデザイナーの田中一光。この二人の
もと、建築家やデザイナー、陶芸家、漆芸家たちが茶
室や茶道具を制作し、出品。デザインの世界に新しい
可能性を示し、クリエーターたちの、後の活動に大き
な影響を与えたと言われる伝説の展覧会だ。その「茶
美会」に...
- 2009年01月09日

パリ・モーターショーにみるオープンカーの台頭
時代と共に新化するオープンカーの数々
2008年9月に開催されたパリ・モーターショーには、環境適合という世界的潮流や米国のサブプライムローン問題から飛び火した自動車業界の大寒波などの暗い雰囲気を吹き飛ばしてくれるニューモデルが一堂に会した。また今回パリに出展された数々の車のなか、爽快で開放感ある走りを満喫できるオープンモデルの車種が、一際目を引いていた。
電動で開閉するメタルルーフを備...
- 2009年01月09日