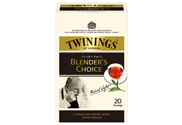創業当初から、赤いビロードの椅子やステンドグラス、壁に掛けられたイタリア・メディチ家の「モナ・リザ」の複製などが、パリのサロンを連想させる優雅な雰囲気の喫茶店であった。今もその贅沢さは健在で、毎日常連のお客さんや観光客でにぎわう。今では、どんなに混んでいても相席をしないというのがフランソアの流儀だそうだ。
●フランソア喫茶室
京都市下京区西木屋町通四条下ル船頭町184 営業時間10:00 ~ 23:00
12月31日・元日休み、夏季休日2日あり
TEL075-351-4042 www.francois1934.com
●フランソア喫茶室
京都市下京区西木屋町通四条下ル船頭町184 営業時間10:00 ~ 23:00
12月31日・元日休み、夏季休日2日あり
TEL075-351-4042 www.francois1934.com
戦後、営業を再開すると、店の南側にミレー書房を開く。本を買った学生や大学教授たちは、隣の喫茶室でたばこの煙をくゆらせながら、ゆっくり本を読み思索にふけったという。ミレー書房の店長は立野の友人の宍戸(ししど) 恭一(きょういち)さんが担当し、一般に
は入手困難な洋書などを取りそろえた。ちなみに宍戸さんは1950年に独立して、寺町通にある三月書房を創業。現在、定評ある独自のセレクションで有名な書店となっている。
再び自由と芸術の薫りがあふれる喫茶店として、フランソアは多くの人々を引きつけた。仏文学者の桑原武夫や、生態学者の今西錦司、東洋学者の貝塚茂樹等の京大の教授たち、仏文学者の多田道太郎(みちたろう)、演劇家の宇野重吉(じゅうきち)、滝沢修、同志社大学で教鞭を執る矢や 内原伊作(ないはらいさく)や鶴見俊輔(しゅんすけ)などが集い、議論や思索、創作が繰り広げられる“文化サロン"となった。
今もなお、客足が絶えない人気の喫茶店であるフランソアを守るのは、立野正一の息子で3代目となる立野隼夫(はやお)社長である。
「父からは『おいしいコーヒーを出せ、店を清潔にしろ、そしてサービスは程々に』ということが遺言だと思っています。なので、これは何があっても守るべきことだと思います。ウチのコーヒーには、フレッシュクリームがたっぷり入っているでしょう。コーヒーが苦手な宇野重吉先生のために、母が考案しました。
春に、息子の寺尾聰(あきら)さんが来店してくださって、感極まりました。母は宇野先生と同郷の福井出身でしたので、劇団民芸を応援していました。今も、2代、3代と通って来てくださる常連のお客さんが多いんです」
立野社長は30代の頃、東京・銀座と成城でフランソアの支店を10年近く経営していた。
「30年前に京都に戻ることになり、洋菓子を基礎から勉強しようと、大阪・あべの辻製菓専門学校に入学した。42歳のことです。
卒業後は、神戸・北野異人館と兵庫・芦屋で合わせて12年ほど洋菓子店を経営し、そこで学び、好評を得た経験をもとに、今ではフランソアで20種にも及ぶ洋菓子を提供させていただいています」
中でも一番人気というレアチーズケーキは、レモンの酸味が効いていて暑い京都の夏にはぴったりの味わい。フランソアのコーヒーとのバランスも抜群だ。
京都でいつの時代も文化サロンとしての役割を担いつつ、地元の人々に親しまれ続けるフランソア喫茶室。この店に残っているそうした内面的な知的で自由を愛する雰囲気こそが、フランソアの創業者、立野正一が吹かせたパリの風、京都の“昭和"だったのではないだろうか。
は入手困難な洋書などを取りそろえた。ちなみに宍戸さんは1950年に独立して、寺町通にある三月書房を創業。現在、定評ある独自のセレクションで有名な書店となっている。
再び自由と芸術の薫りがあふれる喫茶店として、フランソアは多くの人々を引きつけた。仏文学者の桑原武夫や、生態学者の今西錦司、東洋学者の貝塚茂樹等の京大の教授たち、仏文学者の多田道太郎(みちたろう)、演劇家の宇野重吉(じゅうきち)、滝沢修、同志社大学で教鞭を執る矢や 内原伊作(ないはらいさく)や鶴見俊輔(しゅんすけ)などが集い、議論や思索、創作が繰り広げられる“文化サロン"となった。
今もなお、客足が絶えない人気の喫茶店であるフランソアを守るのは、立野正一の息子で3代目となる立野隼夫(はやお)社長である。
「父からは『おいしいコーヒーを出せ、店を清潔にしろ、そしてサービスは程々に』ということが遺言だと思っています。なので、これは何があっても守るべきことだと思います。ウチのコーヒーには、フレッシュクリームがたっぷり入っているでしょう。コーヒーが苦手な宇野重吉先生のために、母が考案しました。
春に、息子の寺尾聰(あきら)さんが来店してくださって、感極まりました。母は宇野先生と同郷の福井出身でしたので、劇団民芸を応援していました。今も、2代、3代と通って来てくださる常連のお客さんが多いんです」
立野社長は30代の頃、東京・銀座と成城でフランソアの支店を10年近く経営していた。
「30年前に京都に戻ることになり、洋菓子を基礎から勉強しようと、大阪・あべの辻製菓専門学校に入学した。42歳のことです。
卒業後は、神戸・北野異人館と兵庫・芦屋で合わせて12年ほど洋菓子店を経営し、そこで学び、好評を得た経験をもとに、今ではフランソアで20種にも及ぶ洋菓子を提供させていただいています」
中でも一番人気というレアチーズケーキは、レモンの酸味が効いていて暑い京都の夏にはぴったりの味わい。フランソアのコーヒーとのバランスも抜群だ。
京都でいつの時代も文化サロンとしての役割を担いつつ、地元の人々に親しまれ続けるフランソア喫茶室。この店に残っているそうした内面的な知的で自由を愛する雰囲気こそが、フランソアの創業者、立野正一が吹かせたパリの風、京都の“昭和"だったのではないだろうか。