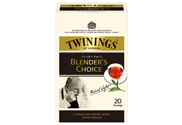喫茶店として日本で初めて文化庁の登録有形文化財に指定されたフランソア喫茶室。1941年の改装の際に創業者の友人、高木四郎やイタリア人の京都大学留学生ベンチヴェンニら芸術家仲間が設計した。「京町屋を洋風に仕立て直したことと、この大きなドーム天井が文化財として評価されました」と立野隼夫社長。

昭和な京都
Part1
Part1
Photo Satoru Seki
フランソア喫茶室
17世紀半ばから18世紀にかけて、イギリスのロンドンで流行した喫茶店――コーヒーハウス。ここでは、もちろん酒は一切出さず、コーヒー、たばこを楽しみながら、新聞や雑誌を読んだり、客同士で政治談議や世間話をしたりしていた。社交場として機能しながら、真剣に交わされた議論やそこから生まれた思想は、近代市民社会を支える世論を形成するという大きな役割を果たした。
こうしてコーヒーハウスは、重要な空間となり、イギリスの民主主義の基盤を育み機能したのだ。それはまさにコーヒーが生み出す文化の力が政治の力として、結実した証しでもあった。
かつて東京にも、こうした喫茶店は確かに存在したが、今はもうない。京都では、ロンドンのコーヒーハウスと同じ役割を果たした喫茶店が今も残っており、“コーヒーは政治を変える力がある"というヨーロッパで生まれた哲学が連綿と受け継がれているのである。
四条河原町から一筋東へ入り、高瀬川に沿って、木屋町通を少し下ったところにある、フランソア喫茶室(以下、フランソア)。1934(昭和9)年に立野 正一(たての しょういち)が創業した。立野は、山口県出身で京都の美術学校出の社会主義者で、同郷の先輩である大塚有章(ゆうしょう)の勧めで、京都帝国大学経済学部教授であった河上肇(かわかみはじめ)の書生兼護衛を務めた人物だ。
店の軒には、スパニッシュの瓦をふき、玄関の扉にはガラスの格子の窓をはめた。内装はイタリアバロック様式のモダンなもので、天井は白いドーム状となっている。漆喰(しっくい)仕上げの壁には、鮮やかなステンドグラスや有名な絵画の複製が掛けられている。店の名は立野が好きだったバビルゾン派の画家のミレーにちなんでフランソアとした。
本格的な名曲喫茶を目指し、電気蓄音機とクラシック音楽の新譜レコードをそろえた。店づくりにはフランスの都、パリに吹く自由、平等、博愛の風を京都にも、という画家志望であった立野の偽らざる気持ちがあったのであろう。当時、友人でもあった画家の藤田嗣治は立野に賛同し、メニューに踊り子のスケッチを残している。
もう一つ、立野には志があった。京大の滝川事件(1933年)などを背景に過酷な言論統制が敷かれていた時代だが、この喫茶店を学生、大学教授、芸術家、文筆家などが自由に政治や思想、芸術を語り合える場として提供するということだ。
店内には、中井正一(まさかず)や斎藤雷太郎(らいたろう)らの反ファシズム誌「土曜日」を置くなど、「軍国主義」に反対し、自由と平和を求める、アカデミックな人々や芸術家などが訪れ、さまざまな議論が交わされた。しかし、こうした立野の活動が治安維持法違反と見なされ、1937年から約2年半投獄される。この間のフランソアは、後に立野の妻となる佐藤留志子さんや数人の店員たちが支え続けた。
こうしてコーヒーハウスは、重要な空間となり、イギリスの民主主義の基盤を育み機能したのだ。それはまさにコーヒーが生み出す文化の力が政治の力として、結実した証しでもあった。
かつて東京にも、こうした喫茶店は確かに存在したが、今はもうない。京都では、ロンドンのコーヒーハウスと同じ役割を果たした喫茶店が今も残っており、“コーヒーは政治を変える力がある"というヨーロッパで生まれた哲学が連綿と受け継がれているのである。
四条河原町から一筋東へ入り、高瀬川に沿って、木屋町通を少し下ったところにある、フランソア喫茶室(以下、フランソア)。1934(昭和9)年に立野 正一(たての しょういち)が創業した。立野は、山口県出身で京都の美術学校出の社会主義者で、同郷の先輩である大塚有章(ゆうしょう)の勧めで、京都帝国大学経済学部教授であった河上肇(かわかみはじめ)の書生兼護衛を務めた人物だ。
店の軒には、スパニッシュの瓦をふき、玄関の扉にはガラスの格子の窓をはめた。内装はイタリアバロック様式のモダンなもので、天井は白いドーム状となっている。漆喰(しっくい)仕上げの壁には、鮮やかなステンドグラスや有名な絵画の複製が掛けられている。店の名は立野が好きだったバビルゾン派の画家のミレーにちなんでフランソアとした。
本格的な名曲喫茶を目指し、電気蓄音機とクラシック音楽の新譜レコードをそろえた。店づくりにはフランスの都、パリに吹く自由、平等、博愛の風を京都にも、という画家志望であった立野の偽らざる気持ちがあったのであろう。当時、友人でもあった画家の藤田嗣治は立野に賛同し、メニューに踊り子のスケッチを残している。
もう一つ、立野には志があった。京大の滝川事件(1933年)などを背景に過酷な言論統制が敷かれていた時代だが、この喫茶店を学生、大学教授、芸術家、文筆家などが自由に政治や思想、芸術を語り合える場として提供するということだ。
店内には、中井正一(まさかず)や斎藤雷太郎(らいたろう)らの反ファシズム誌「土曜日」を置くなど、「軍国主義」に反対し、自由と平和を求める、アカデミックな人々や芸術家などが訪れ、さまざまな議論が交わされた。しかし、こうした立野の活動が治安維持法違反と見なされ、1937年から約2年半投獄される。この間のフランソアは、後に立野の妻となる佐藤留志子さんや数人の店員たちが支え続けた。