

山口県東南部に位置し、瀬戸内海に浮かぶ島では3番目の面積を有する周防大島(すおうおおしま)。島と本土とは大畠瀬戸を渡る大島大橋によって連結している。山岳起伏の斜地で600m級の山々が連なり、その大半が山地だ。年間平均気温15.5℃と比較的温暖な、青く澄みわたる瀬戸内の海と季節ごとの美しい自然が広がる。
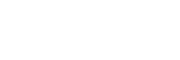
瀬戸内のハワイ・周防大島
遠き異国に夢を抱き、海を渡った勇敢な人々がいた
瀬戸内のハワイと呼ばれる、周防大島。美しい海と温暖な気候に恵まれたこの島をご存じだろうか。山口県の最東端に位置し、瀬戸内海の西に浮かぶ。対岸(本州)の柳井市とは1976年から大島大橋でつながっている。
なぜ、周防大島が “瀬戸内のハワイ"といわれるのか。そのゆえんは、明治時代に頻繁に行われた、日本からハワイへの「官約移民」にある。19世紀半ばから急速に発達したハワイの砂糖産業は、ポリネシア系原住民の人口減少のため、その労働力を海外からの移民に求めた。ハワイ政府はその白羽の矢を日本に立て、日本政府に交渉を重ねた。1884(明治17)年に日本政府は、ハワイへの日本人の渡航を承諾し、募集を開始。すると、第1回の移民募集には予定人数の600人をはるかに超える、2万8000人以上の応募があり、選ばれた944人を乗せたシティー・オブ・トーキョー号は、1885(明治18)年に2週間におよぶ航海を経て、ホノルルに到着した。この第1回官約移民のうち、約3割は周防大島の人たちだったそうだ。以来、移民禁止となった1923(大正12)年まで、26回にわたって官約移民として、約2万9000人の日本人がハワイに渡った。この移民数が最も多かったのが、広島県(1万1122人)、2位が山口県(1万424人)なのだが、周防大島からは県全体の3割以上にも当たる3913人もが移民として渡り、その多くがハワイに永住したという。官約移民では、ハワイ島のプランテーションなどでの3年間の労働が条件。江戸時代中期以降、人工増加が著しかった周防大島からは、働き口がなかった大工や石工、船乗りなどが積極的にハワイへ“出稼ぎ"感覚で渡り、ハワイでは日本の約5倍ほどの賃金がもらえたという。
こうして明治時代からハワイとの交流が深かった周防大島では、1963(昭和38)年には、ハワイ州カウワイ島と姉妹島縁組を結び、文化、産業、スポーツ交流など多岐にわたる交流を展開している。
なぜ、周防大島が “瀬戸内のハワイ"といわれるのか。そのゆえんは、明治時代に頻繁に行われた、日本からハワイへの「官約移民」にある。19世紀半ばから急速に発達したハワイの砂糖産業は、ポリネシア系原住民の人口減少のため、その労働力を海外からの移民に求めた。ハワイ政府はその白羽の矢を日本に立て、日本政府に交渉を重ねた。1884(明治17)年に日本政府は、ハワイへの日本人の渡航を承諾し、募集を開始。すると、第1回の移民募集には予定人数の600人をはるかに超える、2万8000人以上の応募があり、選ばれた944人を乗せたシティー・オブ・トーキョー号は、1885(明治18)年に2週間におよぶ航海を経て、ホノルルに到着した。この第1回官約移民のうち、約3割は周防大島の人たちだったそうだ。以来、移民禁止となった1923(大正12)年まで、26回にわたって官約移民として、約2万9000人の日本人がハワイに渡った。この移民数が最も多かったのが、広島県(1万1122人)、2位が山口県(1万424人)なのだが、周防大島からは県全体の3割以上にも当たる3913人もが移民として渡り、その多くがハワイに永住したという。官約移民では、ハワイ島のプランテーションなどでの3年間の労働が条件。江戸時代中期以降、人工増加が著しかった周防大島からは、働き口がなかった大工や石工、船乗りなどが積極的にハワイへ“出稼ぎ"感覚で渡り、ハワイでは日本の約5倍ほどの賃金がもらえたという。
こうして明治時代からハワイとの交流が深かった周防大島では、1963(昭和38)年には、ハワイ州カウワイ島と姉妹島縁組を結び、文化、産業、スポーツ交流など多岐にわたる交流を展開している。





