

(右)1884(明治17)年創業の「中村茶舗」。初代、中村末吉が、宇治の茶問屋中村藤吉本店から分家し、松江に開業したのが始まり。(左)中村茶舗の奥に構えられた、不昧流の三畳台目の茶室「松吟庵」。松江の茶の湯と菓子の伝統を、旅行者でも気軽に体験できる空間。
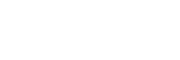
不昧公御好み
Photo Masahiro Goda
Text Rie Nakajima
Text Rie Nakajima
松江は、京都や金沢と並ぶ、菓子どころである。
その背景にあるのが不昧公と、現在も街に息づく茶の湯文化だ。
その背景にあるのが不昧公と、現在も街に息づく茶の湯文化だ。
松江に息づく茶の湯文化
不昧公は、藩の職人たちに茶会で出す菓子を作らせることで、松江に菓子文化を発展させた。現在でも、松江の人々の暮らしには、抹茶と菓子が欠かせない。松江には不昧流を含め、11もの茶道の流派が存在し、日常の中でも難しい作法を抜きにした、茶と菓子が嗜まれている。来客があった時はもちろんのこと、抹茶と菓子を朝食代わりにしたり、夕食後に家族で味わったり。幼稚園から抹茶を飲むプログラムがあるなど、子どもから大人まで、心から抹茶と菓子を楽しんでいる。
現代において、ここまで茶文化が浸透している街はそうはない。それほど、松江の人々にとって不昧公の存在が大きく、時代を超えて親しまれてきたということだろう。
不昧公は、藩の職人たちに茶会で出す菓子を作らせることで、松江に菓子文化を発展させた。現在でも、松江の人々の暮らしには、抹茶と菓子が欠かせない。松江には不昧流を含め、11もの茶道の流派が存在し、日常の中でも難しい作法を抜きにした、茶と菓子が嗜まれている。来客があった時はもちろんのこと、抹茶と菓子を朝食代わりにしたり、夕食後に家族で味わったり。幼稚園から抹茶を飲むプログラムがあるなど、子どもから大人まで、心から抹茶と菓子を楽しんでいる。
現代において、ここまで茶文化が浸透している街はそうはない。それほど、松江の人々にとって不昧公の存在が大きく、時代を超えて親しまれてきたということだろう。





