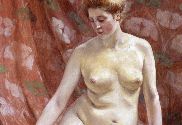(左)河鍋暁斎《河竹黙阿弥作『漂流奇譚西洋劇』パリス劇場表掛りの場》1879(明治12)年 GAS MUSEUMがす資料館蔵 新富座で上演された『漂流奇譚西洋劇』のための行灯(あんどん)絵。生き別れになった親子がそれぞれヨーロッパとアメリカ大陸で冒険を重ねた末に、パリ・オペラ座裏で出会う場面。オペラ座の建物、夫人のドレスの細かい装飾までよく描き込まれている。
(右上)ジョサイア・コンドル《Kyosai sensei at Nikko, Aug.5th》 1885(明治18)年 河鍋暁斎記念美術館蔵 もともと水彩画の素養があったコンドルは、暁斎に弟子入り後は順調に力をつけ、日本画の展覧会で入賞するほどであった。これは、日光に暁斎とともに写生旅行に行った際の暁斎。師弟間の温かい関係を感じる、穏やかな作品だ。
(右下)河鍋暁斎《日光地取》 1885(明治18)年 河鍋暁斎記念美術館蔵 地取(じどり)とは写生のこと。橋を渡るコンドルとその友人、腰を押されて歩く暁斎が描かれている。
(右上)ジョサイア・コンドル《Kyosai sensei at Nikko, Aug.5th》 1885(明治18)年 河鍋暁斎記念美術館蔵 もともと水彩画の素養があったコンドルは、暁斎に弟子入り後は順調に力をつけ、日本画の展覧会で入賞するほどであった。これは、日光に暁斎とともに写生旅行に行った際の暁斎。師弟間の温かい関係を感じる、穏やかな作品だ。
(右下)河鍋暁斎《日光地取》 1885(明治18)年 河鍋暁斎記念美術館蔵 地取(じどり)とは写生のこと。橋を渡るコンドルとその友人、腰を押されて歩く暁斎が描かれている。
「不気味なものに惹かれていた」
このように、オーセンティックな日本画壇、大衆画の世界、外国人という具合に全方位から高い評価を獲得した暁斎は、間違いなく幅広い能力の持ち主であった。そして幅広いだけではない。湧き出るようなエネルギー、個人的嗜好の強い表出といった、きわめてバイタリティーに満ちた絵を描き続けた姿勢もまた、暁斎の特徴と言えるだろう。
暁斎のこのエネルギーの源泉、あるいは個人的嗜好とはどのようなものなのだろうか? コンドルが著書で暁斎を評した言葉「画家としての生涯を通じて、暁斎は不気味で慄然(りつぜん)とするようなものに心惹かれていたようだ」こそ、それを的確に表していると言えるだろう。
暁斎は多くの幽霊画や地獄絵、骸骨画を残している。いずれも当然自発的にではなく注文に応じて描いたものだが、完成度の高さには驚かされる。暁斎の中にある妖しいものへの興味、目を背けたくなる生々しいものへの好奇心があってこその成果だろう。そして、暁斎の描くこれらの画はただ暗く凄惨(せいさん)なだけではない。細部の描写の綿密さ、線の美しさ、デッサンの確かさを備えているので、文字通り目が釘付けになる。
普遍的なのに個性的、アカデミックなのにどこか奇妙、グロテスクなのに美しい―暁斎の技巧や写生力は突出しているが、それらが彼生来の凄惨なものに対する興味と合わさることで、特有のあらがいがたい魅力を備えた作品に結実する。まさに、内なる不気味さを爆発させつつ制御し、「画」という形に完璧に定着させたのが、暁斎の作品。あらゆる情報や刺激があふれる今こそ、私たちの心をつかんで離さない。
●画鬼・暁斎――KYOSAI 幕末明治のスター絵師と弟子のコンドル
会期 2015年6月27日~9月6日(前期8月2日まで、後期8月4日~9月6日)
会場 三菱一号館美術館(東京・丸の内)
開館時間 10:00~18:00(金曜と会期最終週平日は20:00まで)
休館日 月曜(7月20日と8月31日は開館)
問い合わせ TEL03-5777-8600 http://mimt.jp/kyosai
暁斎のこのエネルギーの源泉、あるいは個人的嗜好とはどのようなものなのだろうか? コンドルが著書で暁斎を評した言葉「画家としての生涯を通じて、暁斎は不気味で慄然(りつぜん)とするようなものに心惹かれていたようだ」こそ、それを的確に表していると言えるだろう。
暁斎は多くの幽霊画や地獄絵、骸骨画を残している。いずれも当然自発的にではなく注文に応じて描いたものだが、完成度の高さには驚かされる。暁斎の中にある妖しいものへの興味、目を背けたくなる生々しいものへの好奇心があってこその成果だろう。そして、暁斎の描くこれらの画はただ暗く凄惨(せいさん)なだけではない。細部の描写の綿密さ、線の美しさ、デッサンの確かさを備えているので、文字通り目が釘付けになる。
普遍的なのに個性的、アカデミックなのにどこか奇妙、グロテスクなのに美しい―暁斎の技巧や写生力は突出しているが、それらが彼生来の凄惨なものに対する興味と合わさることで、特有のあらがいがたい魅力を備えた作品に結実する。まさに、内なる不気味さを爆発させつつ制御し、「画」という形に完璧に定着させたのが、暁斎の作品。あらゆる情報や刺激があふれる今こそ、私たちの心をつかんで離さない。
●画鬼・暁斎――KYOSAI 幕末明治のスター絵師と弟子のコンドル
会期 2015年6月27日~9月6日(前期8月2日まで、後期8月4日~9月6日)
会場 三菱一号館美術館(東京・丸の内)
開館時間 10:00~18:00(金曜と会期最終週平日は20:00まで)
休館日 月曜(7月20日と8月31日は開館)
問い合わせ TEL03-5777-8600 http://mimt.jp/kyosai