
(左)金沢大学の前身、第四高等学校は1887(明治20)年に開校。「四高(しこう)」と呼ばれ、「超然」の校風で知られた。現在は石川近代文学館、石川四高記念館となっている。
(右)加賀藩祖前田利家を祭る尾山神社。城下の中心から離れた卯辰八幡宮(現・宇多須神社)で祭られていたものを1873(明治6)年に遷座し、創立した。和漢洋3様式を折衷した神門で有名。
(右)加賀藩祖前田利家を祭る尾山神社。城下の中心から離れた卯辰八幡宮(現・宇多須神社)で祭られていたものを1873(明治6)年に遷座し、創立した。和漢洋3様式を折衷した神門で有名。
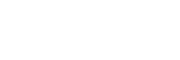
帰りなんいざ、文化満つる街・金沢へ
Photo Masahiro Goda
Text Izumi Shibata
Text Izumi Shibata
「加賀百万石」の印象が強く藩政時代の史跡が注目されがちだが、金沢には明治期の遺構も多くある。それらを巡ると、明治の金沢に生きた人たちへの親愛の情が湧いてくる。
文明開化に乗り遅れて
明治の幕開けは、金沢に活力低下をもたらした。明治維新以降、城下の人口の半分を占めていた武士が俸禄を失うことで、金沢区(金沢城下)全体の経済は停滞する。江戸時代を通じて江戸、大坂、京都に次いで名古屋と同等の都市規模を誇った金沢だが、大政奉還直後は12万3000だった人口が約20年後の市制施行時(1889年)には9万4000人に激減。金沢は文明開化の波に全く乗り遅れたのだ。
打撃を受けたのは士族だけではない。藩の保護を受けていた工芸職人は後ろ盾を失い、自分の生活も技術の伝播(でんぱ)もままならぬ状態に。また歴代藩主の傾倒を受け発展した宝生流の能「加賀宝生」も、藩政終了によりやはり衰退した。その危機を見かね、私財を加賀宝生の支援に投じると決意したのが、地元の履物商にして実業家の佐野吉之助(さのきちのすけ)だ。佐野は加賀藩付きであった能楽指導者を手厚く迎えて自ら技芸を学ぶとともに、1900(明治33)年には能舞台を建設、翌年には金沢能楽会を設立。継続的に加賀宝生を支える体制を整えた。
明治の幕開けは、金沢に活力低下をもたらした。明治維新以降、城下の人口の半分を占めていた武士が俸禄を失うことで、金沢区(金沢城下)全体の経済は停滞する。江戸時代を通じて江戸、大坂、京都に次いで名古屋と同等の都市規模を誇った金沢だが、大政奉還直後は12万3000だった人口が約20年後の市制施行時(1889年)には9万4000人に激減。金沢は文明開化の波に全く乗り遅れたのだ。
打撃を受けたのは士族だけではない。藩の保護を受けていた工芸職人は後ろ盾を失い、自分の生活も技術の伝播(でんぱ)もままならぬ状態に。また歴代藩主の傾倒を受け発展した宝生流の能「加賀宝生」も、藩政終了によりやはり衰退した。その危機を見かね、私財を加賀宝生の支援に投じると決意したのが、地元の履物商にして実業家の佐野吉之助(さのきちのすけ)だ。佐野は加賀藩付きであった能楽指導者を手厚く迎えて自ら技芸を学ぶとともに、1900(明治33)年には能舞台を建設、翌年には金沢能楽会を設立。継続的に加賀宝生を支える体制を整えた。





