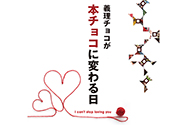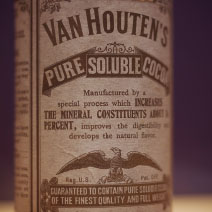

(左)カカオの実の断面。外皮は割と堅いが、中は柔らかでスポンジのよう。平均して30粒程度の種が入っており、これがカカオ豆だ。豆はヌルヌルのパルプ(角皮)に包まれており、ここはブドウのように甘い。またこのパルプが豆の発酵を促す役割を担う。
撮影協力/チョコレート展(2013年2月24日まで国立科学博物館で開催)
撮影協力/チョコレート展(2013年2月24日まで国立科学博物館で開催)

チョコレート、不可思議な食べ物
Photo Satoru Seki Text Fumio Ogawa
日本でチョコレートというと、フランスやスイスが真っ先に思い浮かぶが、オランダでも質の良いチョコレートが数多く作られている。
オランダとカカオといえば、19世紀のクンラート・ファンホーテンの存在が大きい。日本ではバンホーテンと表記され、ココアでその名が知られる技術者である。
ファンホーテンの功績は、カカオからココアバターの抽出に成功したことで、この技術がなかったら、現在のチョコレートは存在しないといってもいいほどだ。
焙煎したカカオ豆をそのまますりつぶし湯に溶いた当時のチョコレートは油っぽいという難点があった。ファンホーテンはカカオの油分を減らすためにカカオマスを搾油。そこからココアという洗練された飲み物を開発した。この時、分離されたココアバターがその後、固形チョコレートの発明に寄与するのである。
スイスもおいしいチョコレートでよく知られた国だ。そもそもチョコレートは、宮廷で広まったのと並行して、宣教師を通じて欧州へと持ち帰られ、修道院などで飲まれていた。眠気を払うようにとコーヒーが好まれたのも修道院だった事実と併せてみると、たいへん面白い。
イタリア・トリノでチョコレート製造技術を勉強していたスイス人、フランソワ・ルイ・カイエがスイスで初のチョコレー工場を作ったのが1819年。そこでチョコレ―トバーの製造に成功した。その後、バニラやシナモンといったフレイバーを加えた製品を出したり、小さなコインのかたちのボンボン・オー・ショコラなどを開発したことが、チョコレートの近代化の貢献として刻まれている。手作業で行われていたカカオ豆の磨砕を水車の力を利用して機械化したのもカイエだった。
並行して、カイエの娘婿のダニエル・ピーターが、ミルクチョコレートを開発したのも、業績向上に大きく寄与した。
どちらかというとビターな、いわゆるクーベルチュール・ノワールが当時最先端のチョコレートだったところに、ピーターは全脂および脱脂をふくめた粉乳を入れたクーベルチュール・オレ、つまりミルクチョコレートの開発に成功した。
通常の牛乳では水分があるため、滑らかなチョコレートにはならない。そこでピーターは粉状の牛乳を使い、ミルクチョコレートを作りだした。
カイエとピーターは、1911年にピーター・カイエ・コーラー・チョコレート会社を設立した。ちなみに29年にはネスレと合併。今でもカイエブランドのチョコレートは発売されている。
チョコレートが欧州にやってくるまでがその歴史の前半部分だとすると、海洋国家でないスイスはそこには登場しない。しかし優れた技術開発力や企画力を武器に、大衆市場の拡大やグローバル化の波に乗って、チョコレートの近代史に大きな足跡を残している。
オランダとカカオといえば、19世紀のクンラート・ファンホーテンの存在が大きい。日本ではバンホーテンと表記され、ココアでその名が知られる技術者である。
ファンホーテンの功績は、カカオからココアバターの抽出に成功したことで、この技術がなかったら、現在のチョコレートは存在しないといってもいいほどだ。
焙煎したカカオ豆をそのまますりつぶし湯に溶いた当時のチョコレートは油っぽいという難点があった。ファンホーテンはカカオの油分を減らすためにカカオマスを搾油。そこからココアという洗練された飲み物を開発した。この時、分離されたココアバターがその後、固形チョコレートの発明に寄与するのである。
スイスもおいしいチョコレートでよく知られた国だ。そもそもチョコレートは、宮廷で広まったのと並行して、宣教師を通じて欧州へと持ち帰られ、修道院などで飲まれていた。眠気を払うようにとコーヒーが好まれたのも修道院だった事実と併せてみると、たいへん面白い。
イタリア・トリノでチョコレート製造技術を勉強していたスイス人、フランソワ・ルイ・カイエがスイスで初のチョコレー工場を作ったのが1819年。そこでチョコレ―トバーの製造に成功した。その後、バニラやシナモンといったフレイバーを加えた製品を出したり、小さなコインのかたちのボンボン・オー・ショコラなどを開発したことが、チョコレートの近代化の貢献として刻まれている。手作業で行われていたカカオ豆の磨砕を水車の力を利用して機械化したのもカイエだった。
並行して、カイエの娘婿のダニエル・ピーターが、ミルクチョコレートを開発したのも、業績向上に大きく寄与した。
どちらかというとビターな、いわゆるクーベルチュール・ノワールが当時最先端のチョコレートだったところに、ピーターは全脂および脱脂をふくめた粉乳を入れたクーベルチュール・オレ、つまりミルクチョコレートの開発に成功した。
通常の牛乳では水分があるため、滑らかなチョコレートにはならない。そこでピーターは粉状の牛乳を使い、ミルクチョコレートを作りだした。
カイエとピーターは、1911年にピーター・カイエ・コーラー・チョコレート会社を設立した。ちなみに29年にはネスレと合併。今でもカイエブランドのチョコレートは発売されている。
チョコレートが欧州にやってくるまでがその歴史の前半部分だとすると、海洋国家でないスイスはそこには登場しない。しかし優れた技術開発力や企画力を武器に、大衆市場の拡大やグローバル化の波に乗って、チョコレートの近代史に大きな足跡を残している。