
かんだ・ひろゆき
1963年徳島県生まれ。大阪の日本料理店で4年半の修業後、1986年にパリの板前割烹「TOMO」の料理長として渡仏。91年に帰国し、小山裕久氏が料理長を務める徳島の料亭「青柳」へ。赤坂の日本料理「basara」の料理長を務めるなど青柳グループの東京進出に尽力。2004年東京・元麻布に日本料理店「かんだ」をオープン。2007年から6年連続『ミシュランガイド東京』で三つ星を獲得。
1963年徳島県生まれ。大阪の日本料理店で4年半の修業後、1986年にパリの板前割烹「TOMO」の料理長として渡仏。91年に帰国し、小山裕久氏が料理長を務める徳島の料亭「青柳」へ。赤坂の日本料理「basara」の料理長を務めるなど青柳グループの東京進出に尽力。2004年東京・元麻布に日本料理店「かんだ」をオープン。2007年から6年連続『ミシュランガイド東京』で三つ星を獲得。
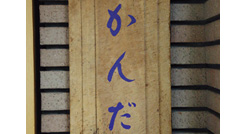

鮎の頭を手前にして、うちわであおぎながら、こんがりと焼く。素人の目には焼き過ぎ?と思えるほど、しっかり焼くのが鉄則だ。焼いている時に落ちた鮎の脂が、鮎の胴体に香りとして付く。
何と言っても鮎は、生きたまま焼かなければね。死んだ鮎は筋肉が硬直して、骨の関節がビシッと締まるため、炭で焼いても骨が口に残るんですね。もちろん身も全然違う。死んだ鮎はペチャッとして、生きた鮎のようにほっこり焼けないんです。それにヒレも、死んだ鮎は立たないので、カリッと焼けません。だからって、塩をこすり付けて無理やりヒレを立たせて焼くと、しょっぱくて食べられたものではないです。川魚って何でも、生きてないとダメですね」
ただ生の状態で見ても、味までは分からないらしい。「あんまり細いと脂がないなとか、肥えていればおいしそうだなとか、体形からイメージされる範囲に限られる」という。
「その鮎のおいしさは、焼いて初めて評価できる」ものなのだ。そして大事なのは「焼き方」。神田によれば「鮎焼きは料理人にとって、『炭扱いの試金石』と言える」技術だそう。
鮎は、自分から出た脂で独自の風味とうまみを作り出す。だからこそ「2匹と同じ鮎はない」。またシンプルな料理法だけに、最も料理人の技術が問われる焼き物でもある。「鮎が気に入ったら、そこを自分の店にするのもいい」と神田は言う。鮎の塩焼きは、鮎自身の個性と料理人の技術、考え方が楽しめる「日本料理の真骨頂」なのである。
●元麻布 かんだ
東京都港区元麻布3-6-34 カーム元麻布1F
TEL03-5786-0150
ただ生の状態で見ても、味までは分からないらしい。「あんまり細いと脂がないなとか、肥えていればおいしそうだなとか、体形からイメージされる範囲に限られる」という。
「その鮎のおいしさは、焼いて初めて評価できる」ものなのだ。そして大事なのは「焼き方」。神田によれば「鮎焼きは料理人にとって、『炭扱いの試金石』と言える」技術だそう。
鮎は、自分から出た脂で独自の風味とうまみを作り出す。だからこそ「2匹と同じ鮎はない」。またシンプルな料理法だけに、最も料理人の技術が問われる焼き物でもある。「鮎が気に入ったら、そこを自分の店にするのもいい」と神田は言う。鮎の塩焼きは、鮎自身の個性と料理人の技術、考え方が楽しめる「日本料理の真骨頂」なのである。
●元麻布 かんだ
東京都港区元麻布3-6-34 カーム元麻布1F
TEL03-5786-0150





