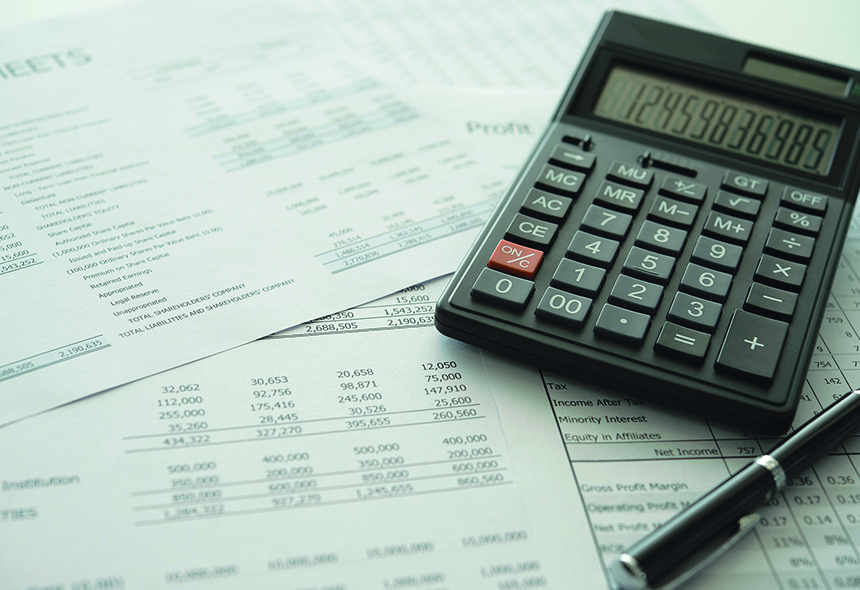

個人海外投資に必要な国際税務の基礎知識
第8回
第8回
永峰 潤 公認会計士・税理士
国際相続に関係する二つの法律(承前)
前回のまとめ
相続が発生した場合、民法と相続税法二つの法律が関係している。相続当事者が全て日本人で財産も国内の場合、相続人の範囲と遺産分割割合は日本の民法のみで解決するが、一旦、外国の要素が入ると外国の民法を検討せねばならない。どちらの国の法律を用いるべきか解決する法律を国際私法といい、わが国では「法の適用に関する通則法」(通則法)が該当する(※1)。そのとき公法たる相続税法はどのように関係するのだろうか。
寄り添わない税法
相続が全て国内で完結する場合は民法と相続税法の間にスムーズな関係が構築されていて人によっては二つの違う法律が適用されているのに全く気付かないかもしれない。しかし相続に外国の要素が入ってくると、とたんにこの関係が崩れてしまうのだ。
被相続人が外国人で遺産未分割の場合、相続人間の遺産分割割合は日本の民法ではなく被相続人の本国法(民法)の規定に従って算出される(前回説明済)。韓国人が被相続人だった前回の例では配偶者60%:子供40%で分割される(日本民法では均等)。
この状態に対して日本の相続税法はどう対応しているか。遺産が未分割の場合は通則法の規定に従い、(被相続人の)本国法の規定で相続人および相続分を基にして各人の課税額を計算することとしている(※2)。このケースならば、配偶者60%、子供40%で各人の課税額を計算し、申告期限(相続開始から10カ月)までに分割割合が決まらない場合はその税額を納めることになる。その後、一定期間内に分割割合が確定した場合は、納めていた税額と確定額とで精算が行われるが、その際の確定額は日本の民法規定によることとされている(※2)。つまり未分割の場合に各人が納める税額は被相続人の本国法によって計算するも、分割が確定した場合の税額は日本の民法に従って計算が行われることになり、わざわざ被相続人の本国法を用いて計算しても、それはあくまで仮の税額という位置づけになってしまう。





