
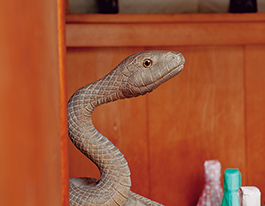

神仏習合のパイオニア
船を降り、港から島を見上げる。急峻な斜面の中腹に立つ朱色の三重塔に向かって、長く急な石段が駆け上がっている。巡礼者や参拝者が祈りを捧げながら上ったことから、「祈りの階段」の名が付けられたという。程なく宝厳寺の本堂に着いた。「弁才天堂」とも呼ばれるここに、秘仏の本尊・弁才天像が祀られている。
弁才天像は、宝厳寺最大の祭礼「蓮華会(れんげえ)」で、人々の代表として選ばれた頭人(とうにん)によって奉納された新造のもの。1000年以上続く祭礼だけにその数は膨大で、内陣裏にも年ごとに新造されてきた多くの像が安置されているそうだ。
開創は724(神亀元)年。聖武天皇が天照大神(あまてらすおおみかみ)のお告げを受けたことがきっかけだと伝えられる。
「江州の湖中に小島がある。その島は弁才天の聖地であるから、寺院を建立せよ。すれば、国家泰平、五穀豊穣、万民豊楽となるであろう」
聖武天皇はこのお告げに従い、僧行基を勅使として遣わして堂塔を開基させた。行基は早速竹生島に渡って草庵を結んで仏道修行をし、四天王像を造立して、小堂に安置した。平安時代になると、竹生島は観音霊場として名を高め、特に天台系の仏道修行の霊地となったのだ。
弁才天像は、宝厳寺最大の祭礼「蓮華会(れんげえ)」で、人々の代表として選ばれた頭人(とうにん)によって奉納された新造のもの。1000年以上続く祭礼だけにその数は膨大で、内陣裏にも年ごとに新造されてきた多くの像が安置されているそうだ。
開創は724(神亀元)年。聖武天皇が天照大神(あまてらすおおみかみ)のお告げを受けたことがきっかけだと伝えられる。
「江州の湖中に小島がある。その島は弁才天の聖地であるから、寺院を建立せよ。すれば、国家泰平、五穀豊穣、万民豊楽となるであろう」
聖武天皇はこのお告げに従い、僧行基を勅使として遣わして堂塔を開基させた。行基は早速竹生島に渡って草庵を結んで仏道修行をし、四天王像を造立して、小堂に安置した。平安時代になると、竹生島は観音霊場として名を高め、特に天台系の仏道修行の霊地となったのだ。





