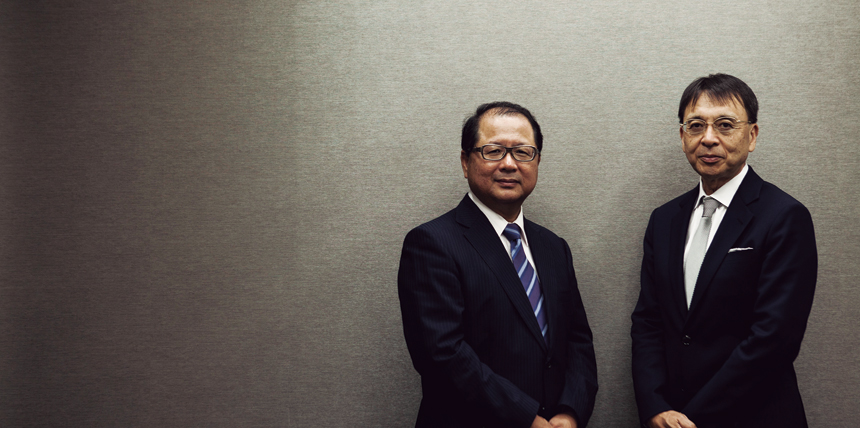
(左)永峰・三島会計事務所 代表パートナー 三島浩光(税理士)(みしま・ひろみつ)中央大学大学院商学研究科修了。公認会計士杉田純事務所(BDO三優監査法人グループ 税務部門)を経て、1998年に三島税理士事務所を設立。2008年より現職。
(右)永峰・三島会計事務所 代表パートナー 永峰潤(公認会計士、税理士)(ながみね・じゅん)東京大学文学部西洋史学科卒業、米ウォートンスクール卒業(MBA)。等松・青木監査法人(現・監査法人トーマツ)、バンカース・トラスト銀行(現・ドイツ銀行)企業金融部を経て、1989年に永峰公認会計士事務所を設立。2008年より現職。
(右)永峰・三島会計事務所 代表パートナー 永峰潤(公認会計士、税理士)(ながみね・じゅん)東京大学文学部西洋史学科卒業、米ウォートンスクール卒業(MBA)。等松・青木監査法人(現・監査法人トーマツ)、バンカース・トラスト銀行(現・ドイツ銀行)企業金融部を経て、1989年に永峰公認会計士事務所を設立。2008年より現職。

海外資産の
相続を迎え撃つ
永峰・三島会計事務所
相続を迎え撃つ
永峰・三島会計事務所
Photo TONY TANIUCHI
Text Junko Chiba
Text Junko Chiba
少しでも有利な投資機会を求めて、世界中の金融商品に投資をしていく。それは、今や日本を含めた世界の「富裕層の常識」である。その際に十分に考慮しておきたいのが、海外分散投資にともなって生じる税金問題だ。とりわけ不幸にして海外資産の相続が発生した場合は手続きが煩雑を極める。前号に続き、この問題に対応する日本でも数少ない税務・会計のプロ集団、永峰・三島会計事務所の二人のパートナーにお話をうかがった。
海外に資産を保有するとはどういうことか、そこを本当に理解している人は少ない。海外で別荘や賃貸住宅等の不動産を手に入れるにせよ、有価証券を購入するにせよ、多くの場合は「上手に資産を守り、運用する」ことで頭がいっぱい。その後、運用益や相続が発生した時に日本の税金が、どのようにかかるかまでは考えが及ばない。実際、相談して初めて、申告や相続の問題が顕在化し、「こんなに大変だったとは」と驚く人がほとんどだという。とりわけ相続については、国によって被相続人のどの財産にどこの国の相続法が適用されるかが異なるので厄介だ。例えば日本では、海外資産を含む全ての財産に日本の相続法が適用されるが、ある国では不動産には所在地の相続法、動産には被相続人の本国の相続法が適用される、といった具合。
「あと大きいのは、プロベート手続きの問題ですね。アメリカやイギリス、シンガポール、オーストラリアなどの国では、裁判所が遺産財団の設置を命じ、そこにいったん借金を含む全ての財産を帰属させてから、裁判所の管理の下で管理清算手続きを行う仕組みになっています。これは非常に手間と時間がかかるので、日本で定められた申告・納税期間に間に合わないこともしばしば。手続きが終わるまで資産を換金できず、延滞税や手続き費用に苦しむ例は少なくありません。私どもはそうした事例も数多く経験していますので、個別の事情に合わせてベストなソリューションを提供できます」と三島浩光氏は言う。
同事務所ではまず顧客と面談して財産の内訳や遺言、信託設置の有無等を聞き、国内外の相続財産の調査と確定、ならびに財産の評価を行う。その上で、日本の相続税を計算すると同時に、海外での相続税あるいは遺産税の申告義務および納税額を把握する。そうして外国税額控除等のもれがないように、日本の相続税を計算する。これらのプロセスの随所で、現地の専門家との協議が必要となる場合がほとんどだ。そこで発揮されるのが上に掲げた同事務所の強み。つまり四半世紀にわたって日本に進出する外資系企業を対象に税務・会計サービスを提供する中で構築してきた専門家の国際ネットワークと、英語による高度なコミュニケーション力である。
「例えばスイスに預金口座があり、かつ不動産を所有しているお客様の場合、現地での確定申告を見なければ、日本での申告もできません。そういう時に専門家ネットワークを駆使して、現地の会計士や弁護士と協業する。こういうことができる会計事務所は日本には少ないのです」と永峰潤氏。海外資産に関する法規制が厳しくなっている状況下、国外財産調書を提出したり、出国税と相続税とが二重の負担にならないよう対策を打ったりする必要が生じる場面は増えることが予測される。そういった制度の対策も包括的に見てもらえるのだから、心強い。できれば海外に資産を持った瞬間から頼りにしたいパートナーである。
「あと大きいのは、プロベート手続きの問題ですね。アメリカやイギリス、シンガポール、オーストラリアなどの国では、裁判所が遺産財団の設置を命じ、そこにいったん借金を含む全ての財産を帰属させてから、裁判所の管理の下で管理清算手続きを行う仕組みになっています。これは非常に手間と時間がかかるので、日本で定められた申告・納税期間に間に合わないこともしばしば。手続きが終わるまで資産を換金できず、延滞税や手続き費用に苦しむ例は少なくありません。私どもはそうした事例も数多く経験していますので、個別の事情に合わせてベストなソリューションを提供できます」と三島浩光氏は言う。
同事務所ではまず顧客と面談して財産の内訳や遺言、信託設置の有無等を聞き、国内外の相続財産の調査と確定、ならびに財産の評価を行う。その上で、日本の相続税を計算すると同時に、海外での相続税あるいは遺産税の申告義務および納税額を把握する。そうして外国税額控除等のもれがないように、日本の相続税を計算する。これらのプロセスの随所で、現地の専門家との協議が必要となる場合がほとんどだ。そこで発揮されるのが上に掲げた同事務所の強み。つまり四半世紀にわたって日本に進出する外資系企業を対象に税務・会計サービスを提供する中で構築してきた専門家の国際ネットワークと、英語による高度なコミュニケーション力である。
「例えばスイスに預金口座があり、かつ不動産を所有しているお客様の場合、現地での確定申告を見なければ、日本での申告もできません。そういう時に専門家ネットワークを駆使して、現地の会計士や弁護士と協業する。こういうことができる会計事務所は日本には少ないのです」と永峰潤氏。海外資産に関する法規制が厳しくなっている状況下、国外財産調書を提出したり、出国税と相続税とが二重の負担にならないよう対策を打ったりする必要が生じる場面は増えることが予測される。そういった制度の対策も包括的に見てもらえるのだから、心強い。できれば海外に資産を持った瞬間から頼りにしたいパートナーである。





