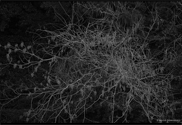(左)柳閣暁粧図 田能村竹田 天保元年(1830) 清雅で淡白な竹田の絵を佐三氏は特に気に入っていた。(右上)絵唐津丸十文茶碗 桃山時代 「これが本物なら、いくらでも持ってこい」と語ったという古唐津。(右下)八ッ橋図屏風(右隻) 洒井抱一 江戸時代 佐三氏亡き後も美術品蒐集は継続された。
主流を離れたものに見出した日本的な美
事業が軌道に乗ってから再び、佐三氏は身の回りに美術品を集めるようになる。あくまでも自分の愉しみのために気に入った品を手に入れており、特に歴史に沿って蒐集するというようなこともなかった。それらは主に九州縁の書画や陶磁器、また中国の陶磁器などであり、趣味は一貫して渋好み。書画であれば田能村竹田を中心とした文人画など、主流から少し離れたものを好んでいた。世間の物差しではなくあくまでも自分の直感に従い、自分の故郷に利するという姿勢は、企業人としての在り方ともつながっているように感じられる。やがて、コレクションがまとまった作家に関しては作品が持ち込まれだし、その質の高さを褒められるようになって自信もついてきた。そのうち美術品を鑑賞できる場を設けてほしいとの要望が出るようになり、1966年、ついに出光美術館をオープン。正統な美術の視点で見ると足りない部分があるとの助言が専門家からあり、総合的に紹介すべきだと考えて、徐々にコレクションを肉付けしていった。